
「僕はカッコいいものを作る、完成度をあげるということに全てを尽くした。それでも残るから、それは汚しても汚しても、汚れない仙田くんらしい部分なんです」
2人組Benlou(ベンルー)がこのたび発表する初EP『煙』の、6曲すべてに宿るいわく言い難いピュアさ、純粋な美しさの理由について聞くと、サウンドプロデュースを手がける山本幹宗(G)はきっぱりそう答えた。
「仙田くん」こと仙田和輝(Vo)は、もともとバンド、アオノオトシゴのヴォーカルとしてプロデューサーの山本幹宗と出会った。そして山本といえば、The Cigavettesとしてデビューした後にくるりや銀杏BOYZ、エレファントカシマシ、never young beachなどでのサポート・ギタリストや様々なプロデュース・ワークなどで多くの音楽人から信頼される、音のプロだ。

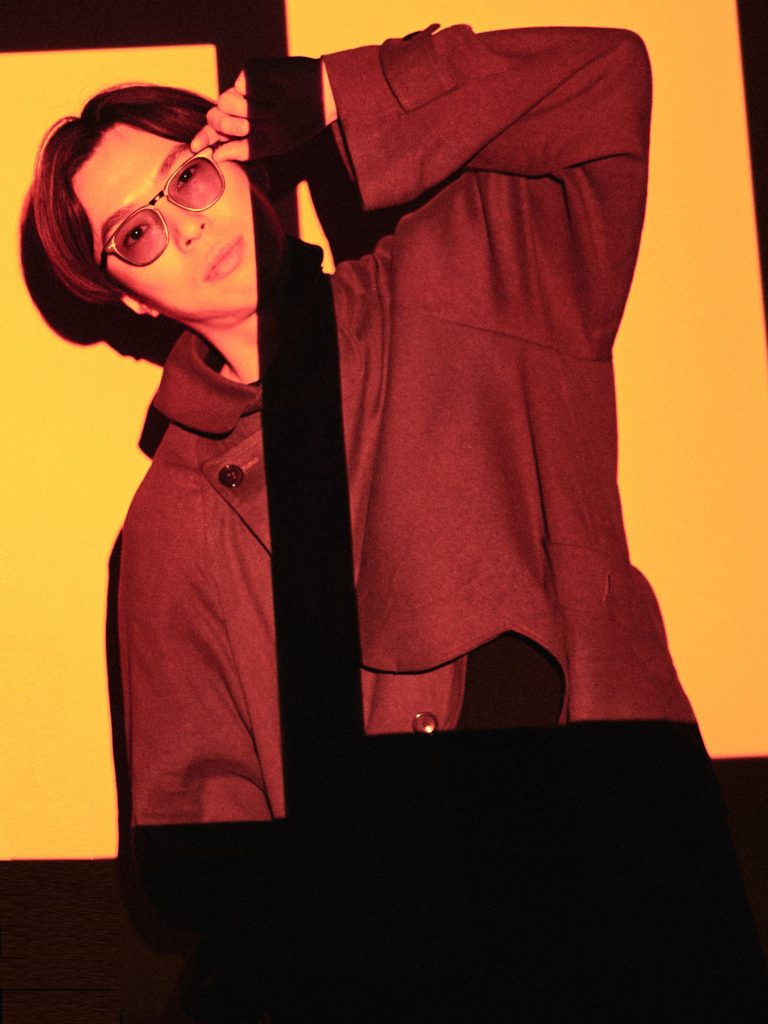
Benlouの活動のスタートは、仙田から届いたこの表題曲の”煙”を聞いたときに、山本が「これはなんとかしなければならない」と決意した地点へと遡る。詳細は後のインタビューにゆずるとして、まずはこの曲を聞いてみてほしい。音楽好きであるほど、仙田による狂おしく切ない旋律と軽やかな歌声、山本の絶妙なさじ加減によるアレンジのマジックで、確かに令和5年の音なのに時代も国も超越してみせるこの名曲の完成度に、刮目せずにいられないはずだ。
山本は否定するかもしれないが、Benlouの音楽が放つ絶妙なピュアさには、彼が手がける音楽がおしなべて持つ純粋さや優しさなどの魅力も一役買っているように私には思えてならない。その証拠に、このEPには彼を知り愛する腕利きの名手たちが勢揃いしてBenlouの門出を飾った。たとえばドラムの屋敷豪太、そしてベースの佐藤征史(くるり)について、日本の音楽好きで知らぬ人はいないはず。この二人がどっしりと、演奏の芯の役割を果たす。
「豪太さんも佐藤くんも癖が強いので、その技やフィーリング、雰囲気を借りたかったです。仙田くんの書く曲は普遍的なポップ・ソングで、だからこそ、そこに二人の性格俳優的なプレイならではのアクの強さが欲しかった」(山本幹宗)
加えて、本作のサウンド・エンジニアには谷川充博、ミックス・エンジニアに宮崎洋一と、幹宗と旧知の敏腕二人も参加している。
「谷川さんは、いわゆるヴィンテージ・サウンドというか、温故知新のちゃんとした音を録ってくれるんです。だから、音の入り口からすごくきれいに太くて、いい音。技術にかけては、とんでもないレベルだと思います。どの曲も僕の録音のこだわりは一緒で、入口はとにかく丁寧な太い音で、というのがポイント。逆にミックスは、何をやってもいいよと。特に何もリクエストせず、『いつも通りにいい感じにしてください』と。僕、基本的にミックス・エンジニアさんには『あなたが思う最高にしてくれ』って言うんです。やっぱり、餅は餅屋ですから」(山本幹宗)
他に初めての顔ぶれとして、ミックス・エンジニアとして参加した小森雅仁やチャーリー・ホルムズらもたまらない化学反応を生んでいるなど、聴きどころがとても多い作品に仕上がった。それを紐解く一端となるよう、それぞれの曲の背景について聞いてみた。
“深部感覚”
――スカとブラスが混じった、独特のゆるやかさを持つ曲ですね。
仙田「幹宗さんと出会って洋楽を積極的に聞くようになった頃に、ふっと浮かんだメロディーの曲です。なので、自分がそれまで作った曲とは毛色が違うんですよね。メロディーの起伏もなく、繰り返しで展開していく曲をイメージしながら作りました。『深部感覚』っていうのは、体内で感じる感覚のこと。例えば、筋が張った感じがする、みたいな内部に生じる感覚のことです」
山本「フィジカルの話なんだ?!」
仙田「はい、もともとはそういう用語なんです。その言葉がふっと浮かんで、それから自分の中にある昔の感覚…感動や情景、幼少期に学校の窓から見た風景みたいに、自分の奥底にある感覚や記憶みたいなものを歌ってみたいなと」
――曲が届いて、山本さんはどういう風にプロデュースしていこうと思いましたか?
山本「メロディーがすごく良かったんですよ。この言葉がふさわしいのかわからないけど、『洋楽的』だなと。一つのメロディーに対してコードが変わっていくのは、洋楽好きが聴き慣れている作りですよね。この曲は歌詞も良かった。この曲だけは俺が歌詞を触ってないですね、仙田くんの歌詞が素晴らしくて。聴いてすぐ頭の中で分解してメロディーとコードだけをイメージしながら…ちょうどその頃ずっと、ブラス・ロック期のシカゴを聞いていたんです。で、頭の中ではすぐこの曲のブラスのメロディーが鳴っていましたね」
――このEPには、他にもブラスを使った曲が何曲かありますよね。
山本「ありますね。それは、ブラス・ロック期のシカゴから始まっています。この曲は特に、間奏のラインを思いついた時、やったぞ俺、と(笑)。実際は生のホーン・セクションに差し替えましたが、デモはいわゆるシンセ・ブラスというか、メロトロンのブラスを使っていました。めちゃくちゃいい音がして、かっこいいんです」
“煙”
――「狂おしい!」と私はメモに書いています。この曲の背景は?
仙田「一言でシンプルに言うなら、叶わぬ恋についての曲ですね。自分が想いを抱いているけれど離れていく相手について、頭の中ではイメージがずっと浮かぶのに、手では触れることができない。そんな相手の姿を、煙になぞらえた曲です」
――仙田さんは自分の体験したことを曲にするほうですか?
仙田「きっかけになるのは、実体験が多いと思いますね。自分の中にあるイメージを、音というものを使って形にするというのが僕にとっての曲作りかな、と」
山本「Benlouはこの曲で全てが始まりました。聴いてすぐ、これは何とかしなければいかんと思ったほど。そこで、曲としてあったものをまずは一回全部バラしました。エモいメロディーというか、良くも悪くもにおうメロディー・ラインだったので、これは真っすぐ作るよりもクールなサウンドにしないと、自分みたいな奴に聞いてもらえないなと。かなりファンキーなカッティングと、ブラスやホーン・セクションを投入しました」
仙田「めちゃめちゃ渋くて、かっこよくなりましたね」
――録音する時、プレイヤーの皆さんにはどういうリクエストを?
山本「デモの時点からドラムは屋敷豪太、ベースは佐藤征史をイメージして、自分がよく知っている彼らのプレイをそのまま落とし込んでいました。だから録音では、好きなようにやってもらうだけでめちゃくちゃかっこいいものになりましたね」
――この曲はハタヤテツヤさんがオルガンを弾いていますね。
山本「ハタヤさんも何度か、くるりやネバヤンでご一緒したことがあって。渋いプレイをされるじゃないですか、あのスモーキーなプレイやフィーリングが欲しくて。それを言ったら、本人には首をかしげられましたけど(笑)。具体的に言って、と言われて『えっと…エレガントの逆』って(笑)」
――そしてこの曲のミックスは小森雅仁さんで。
山本「小森さんはすごいです!令和のジョン・レッキーというか。完璧でした、びっくりしました」
仙田「解像度というか、隅々まで繊細に磨き上げてくれるというか」
山本「いい意味で、いびつさがなく、すごく整っているんですよね。それでいて、昔の音楽から色々知っていると思うので、僕が仕掛けたことに対して毎回的確なアプローチをしてくれるんですよ」
――この曲に限らず、「やられた!」と思った小森さんからの返しを教えてもらえますか?
山本「“ミラージュ”の時に一応『ストーン・ローゼズっぽい感じ』って言ったんですけど、本当にそうなってびっくりしました(笑)。リヴァーブの感じとか絶妙で。僕はあの時代のプロデューサー、スティーヴ・リリーホワイトとかジョン・レッキーとかの音が大好きなんですけど、今あれをやってくれる人がいるんだと。小森さんは僕の持っている感覚にとても近い。僕の頭の中で鳴っている音をそのまま取り出した、みたいな感覚は初めてです。でも、“煙”はレコーディングが大変だったんですよ、ねえ仙田くん。とんでもない出来事が起こりました」
仙田「はい、“煙”は僕、何回歌ったかと思うほど(笑)。なかなかOKが出ず、計三日間に分けてやりました」
山本「もっといいものができるだろう、と。いい感じにオケが仕上がっていたので、それに相応しい歌を細かくディレクションしながら作りました。その場ではできなかったんですよ、なので家に帰って練習しよう、と。毎日朝の10時から夜の7〜8時までやって、何日かおいて、またスタジオに入って」
仙田「何日か置いている間は、練習したり、自分で録った歌声のデータで、ここはまだダメだなとか、ここはもっとできるなとかやってました」
山本「神田川に向かって歌ったりとかね(笑)」
仙田「(笑)神田川の夕陽に向かって」
“ミラージュ”

――この曲は映画『パリ・テキサス』に影響されたそうですね。
仙田「はい、幹宗さんに教えてもらった映画の『パリ・テキサス』を見たのが曲のきっかけです。遠く離れてしまった人への忘れられない気持ちを、ミラージュ、つまり蜃気楼に重ね合わせて書いた曲ですね」
――”Ripple Mark”も”ミラージュ”も、そもそもどうしてこんな素敵な単語を知っているんですか?
仙田「(笑)ありがとうございます。自分の興味関心と紐づいているところはあるかな、と思います。僕は学生時代に海や自然のことを学んできたからか、自然現象に関する言葉にけっこう敏感で。そこからインスピレーションを得ることが多いんだなって、改めて思います。学んできたことが、どこかで影響しているのかな、と」
――山本さんは仙田さんからこの曲が届いたとき、どう思いました?
山本「これは元々の曲調が全く違うんです。メロディーとコード感だけいただきましたね。もっとカーペンターズみたいだったんですよ。そこから、グルーヴをどうしようかなと。僕はビートからアレンジを作るんですけど、これは(ザ・ストーン・ローゼズの)“ウォーターフォール”みたいにできるな、と思った4分後くらいに完成してました。”ウォーターフォール”のあの感じにきれいなメロディーが乗ったら、すごくいいものになるんじゃないかと。音も、いわゆるその時代のロー・ピッチのタムとか、低い音のスネアにしてあって、80年代後半にビートルズを好きな人たちがやってたサウンド…The Dukes of Stratosphear(XTCの変名バンド)とかのサウンドにかなり近いですね。谷川さんはその時代の人なので、まさに『がってん!』という感じ。豪太さんも『じゃあちょっと待っててー』ってタタタタタと」
――屋敷豪太さんはシンプリー・レッドの人ですしね!
山本「そう、まさにあの頃の人だから。その二人が、タイム・スリップしたようにあの頃の音を持って来れる。だから、これはコスプレじゃなくて本物なんです。佐藤くんも着くなり、『俺は(ザ・ストーン・ローゼズの)マニをやったらええやろー』って(笑)。豪太さんはレニをやると。じゃあ俺はジョン・スクワイア、って(笑)」
――イアン・ブラウンは大変だと思います(笑)。
仙田「(笑)なりきれなかったですね」
山本「あと、この曲はビートルズの“マザー・ネイチャーズ・サン”のギターのアルペジオにもインスパイアされています。序盤はもじっていて、アウトロは全く一緒。それと、とにかく小森さんの素晴らしいサウンド。アウトロの演奏が消えていく中で、リヴァーブのサウンドをデカくしてくれ、って一つだけリクエストしたんですよ。(ザ・ストーン・ローゼズの)“アイ・アム・ザ・レザレクション”のあの感じにしたいと思って。それが完璧に思った通りになった。本当すごいなと」
“フェイク”
――この曲は、不穏な空気が響いてきます。
仙田「優しさとか好意の裏側にある、真意とか意図とは一体なんだろうという、ひねくれた、怖いテーマの曲です(笑)。向けられた優しさがどこまでいったい本物なのか、と。今ってSNSや身近な場所など、いろんなところでいろんな人が繋がったりアプローチする中で、いろんな優しさが見える。心からの優しさもあれば、個人的な利益というか、野心みたいなものが見え隠れする優しさもあったりするところから書き上げた曲です。優しさの裏にある別の感情に対するやるせなさを、自分の中で形にしたかったのがきっかけですね」
――この曲が届いた時、山本さんはどう思いました?
山本「これはEPの6曲の中で一番、仙田くんの元のデモに近いですね。まず歌詞が最初からかっこよかった。一行目の言葉を少し変えただけで、基本的には頂いたものをほぼそのまま使っている。サウンドに関しては、仙田くんから送られて来たやつがVシネのサウンド・トラックみたいだったんですよ(笑)。僕の親父が家でよく日曜にVシネを見てたんすよね。特にブラスのラインは、かなりそういうイメージです。アーシー、砂埃、強めのビート…というか。レコーディングもスムーズでしたね、シンセサイザーのアレンジの半分は仙田くんがやっているんですよ。仙田くんのデモに入っていたシンセや、仙田くんの作った転調も生かしてます」
――プレイヤーの皆さんには、どういう言葉で?
山本「『Vシネみたいな感じで』と伝えました。佐藤くんには『ようわからんけど、やってみるわー』って言われました(笑)。で、豪太さんはVシネの時代に日本にいなかったんです(笑)。だから、アウトローな感じ、ニューヨークのスラム、悪い感じ、とか説明したら『あーOK OK、あの感じね!』って。俺はそれ聞いて、え、どういう感じをイメージしてるんだろうと(笑)」
仙田「カーン、ってやってましたね、乾いた感じで、悪いスネアを」
山本「うん。オールド・スクールなヒップホップのビートとかを合わせた感じでしたね。佐藤くんはスラップとかもやってくれて、ひたすらファンキーに。で、僕はこの曲はサビにちょっとカッティングを弾いただけなので、ほとんど何もしてないという(笑)」
“路地裏”

――これもまたいい曲ですね。海外の方が聞いたら、とても日本的だけど、彼らの知る海外の要素、我々にとっての洋楽感も聞こえると思う。シティ・ポップでもなく、歌謡曲だけでもない、個性を感じます。
仙田「自分の中には、『歌謡曲っぽいメロディー』というイメージがありました。最近、一部で令和歌謡って言われている、マイナー調な曲が増えてきたなと感じたことがあって。その頃にヒットチャートにあった曲から間接的な影響を受けて、自分もマイナー調で、少し哀愁の漂う曲を描いてみたいと思ってできた曲です。そこに幹宗さんのワールドワイドな、幅広いアレンジのテイストがうまく融合したことで新しい質感が生まれたのかな、と僕は思いました」
――山本さんは、アレンジに悩んだりはしませんでした?
山本「これはこうするしかない、という一択でした。どうやっても憂いを感じるものになるので、極力ファンキーなものにしたいと。基本はR&Bですね、オルガン・ソロがあって…この曲の感じでギター・ソロを弾いちゃうと、とんでもないことになるから。あと、間奏にはトリッキーな転調を入れて、真っすぐにエモくは聞かせない工夫もしました。間奏でまず一回クールダウンしようと、オルガン・ソロが入る前に一音上に転調してるんです。で、そのままの勢いでオルガン・ソロが始まるんですけど、ソロの間に一音下がって元に戻る。要は『お前ら落ち着けよ』、っていう(笑)。そのまま上へ上へと行かせない工夫をしましたね。一旦そこで気持ちを止めて、また次のブリッジに行く、と」
“Ripple Mark”

――この曲が、8月23日の記念すべき初のシングルでした。
山本「曲を聞いて、俺が『この曲をファーストシングルにする』って決めたんです。デモを作っている時から決めていた」
仙田「そう言われた時は、すごく嬉しかったですね。もっと何往復もやりとりしながら苦戦するかと思ってたんですけど、一発で『これだ』と」
山本「『仙ちゃん、これや」と」
仙田「嬉しかったです」
――アレンジはすぐにできました?
山本「これは一瞬でできました。調子良い時は、パッと聞いてインスピレーションが浮かんで、小一時間でできちゃうんですよ。ツルッとできましたね。仙田くんからは相当な数の曲をいただいているんですけど、中でもこの曲はあっという間にできました」
仙田「この曲をレコーディングした時は、僕は初めての歌録りだったこともあって、すごく緊張しましたね。唄っていても不安定になっちゃう。じゃあ一行ずつ細かく録っていきましょうか、と谷川さんにゆっくり付き合ってもらっていたんですけど、時間もかかっちゃって。次第に僕も気持ちが追い詰められて、で、『もう一回お願いします』と立て続けにお願いしてたら、ちょっと待って、疲れた、いい加減休ませて、ってことに。本当に、僕にとってとても勉強になりました」
――この曲のミックスはチャーリー・ホルムズ。この人は?
山本「この人は、マーク・スパイク・ステント(オアシス、マドンナ、エド・シーランらのサウンド・エンジニア)の弟子です。色々やっているんですが、僕はその中でもPeach Tree Rascalsが一番ピンときた。アン・マリーも一曲やってますね」
――では、この曲のサウンドでイメージしたもの、というと?
山本「Peach Tree Rascalsみたいな最近のアメリカの西海岸サウンドと、あとはCP-80ですかね。これはヤマハの80年代のエレクトロニック・ピアノで、当時海外のアーティストたちがよく使っていたんですけど、とんでもなくバブリーな音がするんですよ。癖がありすぎていろんなものには使えないエレピなんですが、その音が僕は好きで。そのサンプリングした音源を谷川さんが持っていたので、使わせていただきました。おかげでとてもキラキラしましたね」
絶妙なブラス・サウンドと一度聴いたら耳から離れないサビが陰影を織りなす”煙“、軽やかで伸びやかな“ミラージュ”、不穏な空気を漂わせる”フェイク“。令和歌謡の代表曲となるであろう”路地裏“などなど、どの曲もそれぞれ個性的で、聴き込みたくなる音楽的な仕掛けや、耳が喜ぶ響きを様々なスタイルで宿している。
そんな曲たちに共通する点を挙げるとするなら、ミドルエイトの存在をはじめ、後半へ向かって聞き進めるほどに狂おしさが倍増していく点だろう。いわゆるストリーミング時代の曲の特徴である、短いイントロで前半に盛り上がる、というのとは少し異なる。「前半もいいが後半もいい」のが、Benlouの曲だ。
凄腕のプレイヤーやエンジニアたちと共に作り上げた、かけがえのないこの初EP『煙』。冒頭にも書いたいわく言い難い純粋さやピュアさが本作には宿るからか、聴いているこちら側の「音楽好き」な好奇心まで純化されていくかのよう。本作には一度聴くだけでも感動と驚きがあり、聴けば聴くほどに発見と喜びがある。ぜひ、体験してみてほしい。
TEXT 妹沢奈美